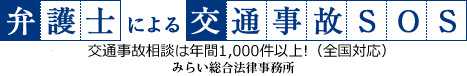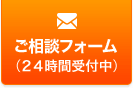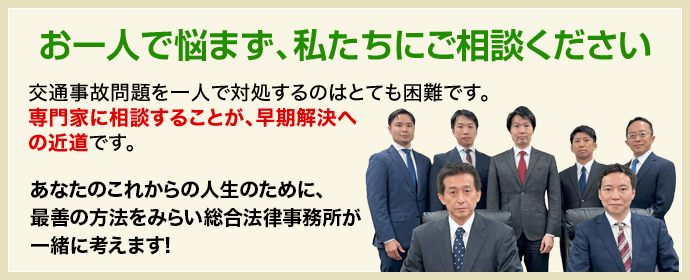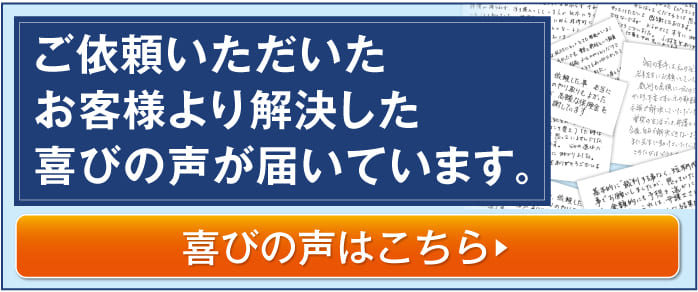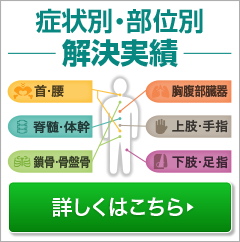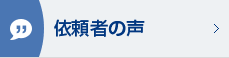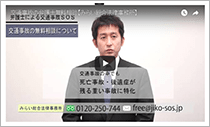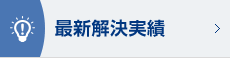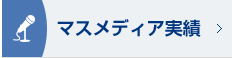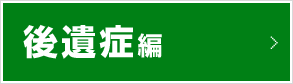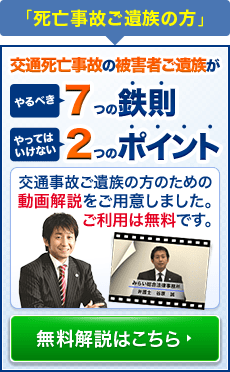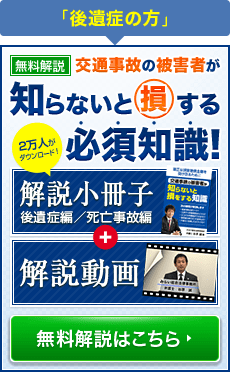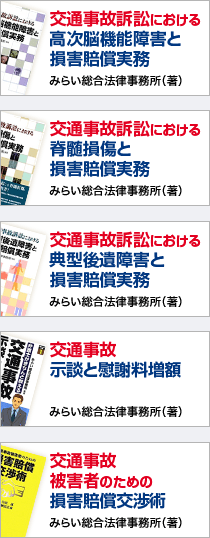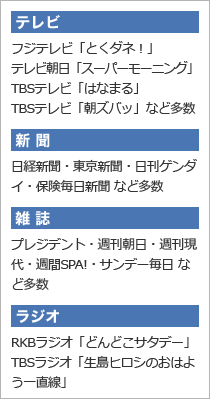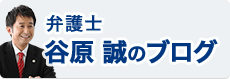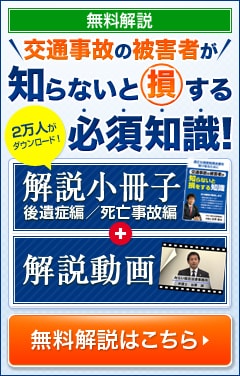交通事故における休業損害(休業補償)まとめ
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
交通事故の被害でケガをして後遺障害が残ってしまった被害者は、加害者側の任意保険会社などと示談交渉をしなければいけません。
請求できる損害賠償としては、逸失利益や慰謝料、治療費など、多くの項目におよびますが、今回は、そのうち、「休業損害」について解説します。
休業損害の仕組みと内容から、損害として認められる条件や金額までを見ていきます。
目次
損害賠償金には慰謝料以外にもさまざまな項目がある!
交通事故の被害者が受け取ることができる損害賠償金の項目には、治療費や入院費、通院交通費、慰謝料、逸失利益など、さまざまなものがあります。
ところで、これらの損害項目を理解するうえで注意するべきことがあります。
それは、損害項目には「積極損害」と「消極損害」と呼ばれるものがあるということです。
積極損害とは、被害者が現実に支払った、または支払いを余儀なくされる金銭のことです。
積極損害に該当する項目としては次のものがあげられます。
①治療費
②付添費
③将来介護費
④入院雑費
⑤将来雑費
⑥通院交通費
⑦装具・器具等購入費
⑧家屋・自動車等改造費
⑨葬儀関係費
⑩損害賠償請求関係費用
⑪弁護士費用
詳しい解説はこちら⇒
「交通事故の治療費や入院費などは、どこまで損害賠償請求できるのか?」
一方、消極損害とは、加害行為がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害のことをいいます。
消極損害には、休業損害の他に慰謝料や逸失利益などがありますが、それぞれが非常に重要な損害項目のため、ここではまず休業損害について説明していきたいと思います。
休業損害が認められる条件や金額は就労形態によって違う
休業損害とは、交通事故で負ったケガの治療などのために仕事を休んだことによって得ることができなかった利益=労働収入のことです。
休業損害は、就労形態等によって算定方法が異なるため、ここでは就労形態別に説明をします。
①給与所得者
【認められる金額】
交通事故前の収入を基礎として、ケガによって休業したことによる現実の収入減。
【認められる条件】
ケガを原因として休業したこと。
会社員や公務員のような給与所得者の場合、交通事故前の収入を基礎としてケガによって休業したことによる現実の収入減が休業損害となります。
事故前の収入は、事故前3ヵ月の平均給与をもとに算定することが一般的で、計算式は次のようになります。
3ヵ月の給与額の合計額 ÷ 90日 × 休業日数
仕事内容等によって季節的に給与額が大きく変動する場合には、直近の3ヵ月の平均賃金とせずに、前年の同期の収入を参考にすることがあります。
なお、有給休暇を使用した時も休業損害と認められますし、休業に伴う賞与の減額・不支給や昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められています。
「当法律事務所の解決事例」
23歳男性が、原付バイクで直進中、停車中の自動車のドアが突然開き衝突した交通事故で左前腕骨骨折や鎖骨骨折などのケガを負ってしまいました。
男性は、機能障害と神経症状の後遺障害が残り、自賠責後遺障害等級10級10号と14級9号の併合10級が認定されました。
加害者側の保険会社との示談交渉では、示談金として461万3643円が提示されましたが、男性にはこの金額の妥当性がわからなかったため当法律事務所の弁護士に相談したところ、増額は可能との見解だったために依頼することを決断。
弁護士と保険会社との間では休業損害と慰謝料額が争点となりましたが、最終的には約4.8倍の増額に成功し、2222万1043円で示談が決着しました。
詳しい解説はこちら⇒
【後遺障害】併合10級で4.8倍に増額
②個人事業者
【認められる金額】
交通事故の前年の確定申告所得を基礎として、ケガにより就労できなかった期間。
また、休業中の固定費(家賃や従業員給料など)。
【認められる条件】
ケガによって就労できなかったこと。
休業中の固定費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものであること。
自営業者や自由業者などの事業所得者は、給与所得者のように容易に休業損害について算定できないこともあります。
収入の証明には、通常は事故の前年の確定申告書に記載してある所得額を基準とします。
実際の所得額よりも低く申告しているケースでは、申告額以上の収入があったことを帳簿や請求書、領収書等の資料から確実に証明できた場合には、申告額を超える収入額が認められる場合もあります。
しかし、節税対策などのために収入を過少に申告しているようなケースでは、裁判所としても、納税義務をきちんと果たしていないのに損害金だけは実際の収入額に応じてもらえる、というような事態を安易には認めるわけにはいかないので、証明のハードルはかなり高くなります。
そうした場合には、修正申告を行なって税金をきちんと納めることも検討する必要があります。
なお、確定申告をしていない場合でも、相当の収入があったと認められる時には、賃金センサスの平均賃金を基礎として休業損害を算定することが認められています。
ちなみに、賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめたもので、たとえば「日本人で、30歳の会社員であれば平均賃金が〇万円」というように、就労形態別の労働者の賃金の実態がわかるようになっています。
③主婦
【認められる金額】
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎として、ケガのため家事を行えなかった期間。
【認められる条件】
ケガを原因として家事を行なえなかったこと。
主婦は、家事を行なっていても、その対価として現実的に金銭を受け取っているわけではありません。
そのため、主婦には休業損害はないと思っている方もいるかしれませんが、主婦でも休業損害は発生します。
なぜなら、事故の影響で家事を行なえなくなれば、誰かがそのしわ寄せを受けることになりますし、場合によっては、家政婦などを頼まざるを得ない事態も考えられるからです。
つまり、主婦業も金銭的に評価されるのです。
主婦の場合、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎として、ケガのために家事を行なえなかった期間について認められます。
④会社役員
【認められる金額】
交通事故のケガによって就労できなかった期間の労務提供の対価部分。
【認められる条件】
ケガを原因として就労できなかったこと。
会社の取締役などの役員が受け取る報酬としては、利益配当的な部分と労務の対価としての給与部分に分けることができます。
労務の対価としての給与部分は、就労不可能になり会社から支給されなくなれば、当然その分が休業損害と認められます
しかし、利益配当的な部分は、働くかどうかに関係ないので、休業損害とは認められません。
問題は、この労務提供の対価部分の金額です。
実際には明確に算定することが困難なため、賃金センサスの平均賃金を参考にしつつ、会社の規模や被害者の役割などを総合的に考慮して、労務提供の対価部分を算出することになります。
⑤失業者
【認められる金額】
交通事故のケガによって就労できなかった期間について、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額。
【認められる条件】
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる者であり、かつ、受傷によって就労できなかったこと。
失業中の人には原則として休業損害は発生しません。
休業損害とは事故による現実の収入減に対して認められるものですが、失業者には現実の収入減がないからです。
しかし、就職活動を行なっていたり、就職が内定していたというように労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には認められます。
基礎となる収入額は、実際に就職先が既に決まっていた場合には、その就職先の給料が基礎となります。
就職活動中で、まだ就職先が決まっていなかった場合には、就労の確実性が低いとされ、賃金センサスの平均賃金あるいは平均賃金の7、8割程度を基礎として認められる可能性があります。
⑥学生や幼児など
【認められる金額】
原則として認められないが、収入があれば交通事故のケガによって就労できなかった期間の収入。
【認められる条件】
収入があり、ケガによって就労できなかったこと。
学生や幼児の場合は、収入がないので原則として休業損害は認められません。
ただし、学生でアルバイト収入があった場合は、休業損害として認められる可能性があります。
また、事故によるケガのために就職活動ができず、就職が遅れてしまった場合には、賃金センサスの平均賃金に基づいて、就職が遅れた期間についての休業損害が認められる可能性があります。
このように、交通事故の被害者の休業損害額の算出については、計算方法が複雑で難しいいため、被害者が1人で示談交渉していくのは難しいと思います。
やはり、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうが、精神的なストレスから解放されて、しかも損害賠償金が増額する可能性が確実に高くなります。
加害者側の保険会社との示談交渉は、ある意味で戦いでもあります。
被害者の方は、1人で悩んだり、苦しまないためにも、まずは一度、弁護士に相談されることをお勧めします。